第1話:君の指先、銀の鈴
「……あ、もうこんな時間」
駅へと続く坂道を走りながら、佐藤美咲は手首の時計を横目に小さくため息をついた。 都内のデザイン事務所でアシスタントとして働く彼女の毎日は、締め切りと修正依頼の繰り返し。おまけに「お人好し」な性格が災いして、先輩から押し付けられた雑務で昨夜も残業だった。
(でも、この時間だけは譲れないんだよね)
美咲は少し乱れた息を整えながら、いつもの3番ホーム、端っこにある3番目の柱の前に立った。
そこには、今日も「彼」がいた。
名前も知らない。けれど、いつも古いタイプの有線イヤホンで音楽を聴きながら、文庫本の世界に没頭している彼。 美咲はデザインの仕事で鍛えられた観察眼で、つい彼の様子を追ってしまう。 (今日は少し厚めの本だ。ページをめくる指、相変わらず綺麗だな……)
美咲にとって、彼を遠くから眺めるこの数分間は、殺伐とした仕事モードから自分を解放してくれる、大切な「日常のピース」だった。
ところがその朝、予期せぬトラブルが起きた。 急な激しい雨のせいで電車が遅れ、ホームは避難してきた人々でごった返したのだ。
「わっ……!」
背後から押され、美咲の体がつんのめる。 その拍子に、バッグにつけていたお気に入りの「銀の鈴」が、千切れて足元へ転がっていった。おばあちゃんから譲り受けた、美咲にとって唯一のお守り。
「あ、待って……!」
人混みの足元をすり抜け、線路の方へ向かっていく銀色の光。 焦って手を伸ばそうとしたけれど、周囲の傘や鞄に阻まれて身動きが取れない。 (どうしよう、あれだけは失くしたくないのに……!)
視界が不安でじわりと滲んだ、その時だった。
スッと、見覚えのある長い指が、その鈴を拾い上げた。
「……これ、君の?」
低いけれど、どこか温かい声。 顔を上げると、そこにはいつも本を読んでいる彼がいた。 イヤホンを片方外し、少し困ったように眉を下げて、彼は美咲を見つめていた。
「あ……はい、そうです。ありがとうございます……!」
美咲は、拾ってもらった鈴と、初めて間近で見る彼の瞳を交互に見つめることしかできなかった。 雨音にかき消されそうなほど小さな声だったけれど、二人の間の境界線が、確かに解けた音がした。

第2話:しおりが挟まった、君の秘密
「あ、ありがとうございます……!」
震える手で鈴を受け取ると、指先がほんの少しだけ触れた。 デザインの仕事でいつも色や形を細かく見ている美咲の目には、彼の指の節や、爪の形までもが鮮明に焼き付いてしまう。
(熱い。私の顔、今絶対リンゴみたいに赤い!)
美咲は心の中で絶叫しながら、必死に視線を泳がせた。すると、彼の左手に握られた一冊の本が目に入る。
「あの……その本」
「え?」
「……私も、持ってます。その作者さんのファンで、装丁の色使いも、すごく素敵だなって思ってて」
美咲は口にした後で、「デザイナー気取りなこと言っちゃった!」と激しく後悔した。けれど、ハルキさんは意外そうに目を丸くした後、今日一番の穏やかな笑顔を見せた。
「……本当? これ、少し古い本だし、周りに読んでる人いなくてさ。なんか、嬉しいな」
そう言って、彼は挟んでいた「しおり」を指でなぞった。 いつもは音楽の壁を作って、周囲を寄せ付けない雰囲気だった彼が、今はまるで同じ秘密を共有した仲間を見るような目で、美咲を見ている。
「私、その人の新作が出るたびに、表紙の紙質までチェックしちゃうんです」
「はは、マニアックだね。でも、分かるよ。……あ、もう電車来ちゃうな」
遠くから、電車の走行音が響いてくる。 美咲は、このまま名前も知らずに別れるのが急に怖くなった。お人好しでいつも一歩引いてしまう自分だけど、今だけは、ほんの少しの勇気が欲しい。
「あの!……私、佐藤美咲っていいます。隣のデザイン事務所で働いてて……」
勢いよく名乗った美咲に、彼は一瞬驚いた顔をしたが、すぐに優しく目を細めた。
「……ハルキ。名字は、また今度。……じゃあね、美咲さん」
彼はそう言い残すと、滑り込んできた電車の列に飲み込まれていった。 手に残った鈴の感触と、初めて聞いた「ハルキ」という名前。 美咲は、混み合う車内でも、自分の頬がずっと熱いままなのを感じていた。
第3話:コーヒーの香りと、震える指先

ハルキさんと名前を交わしてから、数日が過ぎた。
美咲は、昨日までの自分とは少し違う。修正依頼の山に埋もれていても、ふとした瞬間に手のひらの「鈴」を見つめては、彼の低い声を思い出して背筋を伸ばしていた。
(お礼、やっぱりした方がいいよね……。でも、いきなり何か渡すのは変かな?)
お人好しで考えすぎてしまう美咲は、昨夜、近所のコーヒーショップで1時間も悩んだ。結局選んだのは、仕事の合間に一息つけるような、少し高級なドリップバッグのセット。
「……あ、いた」
いつもの3番ホーム。 ハルキさんは、今日も定位置に立っていた。 けれど、美咲のデザイナーとしての観察眼が、すぐに「いつもと違う点」を見つける。
(……今日は、本を読んでない?)
いつもは周りを拒絶するように本の世界に没頭している彼が、今日は手元を見つめたまま、心なしかソワソワしているように見えた。
「……おはようございます、ハルキさん」
勇気を出して声をかけると、彼は弾かれたように顔を上げた。
「あ……おはよう、美咲さん。今日は、ペン、耳に挟んでないんだね」
「えっ!? あ、恥ずかしい……! 前はそんな姿を見られてたんですね」
美咲は顔を真っ赤にして髪を整えた。ハルキさんは、いたずらっぽく、でもどこか安心したように笑った。
「あの、これ……先日のお礼です。ハルキさん、いつも本を読まれているから、コーヒーとか合うかなって」
紙袋を差し出す美咲の手が、緊張で少し震える。 それを受け取ろうとしたハルキさんの手も、わずかに震えていることに、美咲は気づいた。
「……いいの? 嬉しいな。ちょうど、今朝は少し冷えるなと思ってたから」
ハルキさんは受け取った袋を大事そうに抱え、少し言いよどんだ後、決心したように口を開いた。
「……実はさ、俺、今朝は本を読むのに集中できなくて。……君が来るのを、ずっと待ってたから」
「え……?」
予想外の言葉に、美咲の思考が止まる。 ハルキさんは気まずそうに視線を逸らすと、カバンから一冊の本を取り出した。
「これ、俺の名字。……そこに書いてあるから。読み終わったら、また感想教えてくれる?」
手渡された本の見返しには、丁寧な字で『一ノ瀬(いちのせ)』と書かれた蔵書印が押されていた。 「また今度」と言っていた名字を、彼はこんな形で教えてくれたのだ。
電車の到着を知らせるアナウンスが響く中、美咲は彼から借りた本の重みを、大切に胸に抱きしめた。


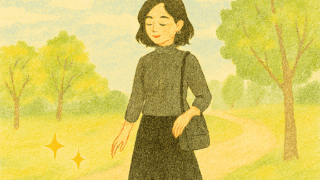
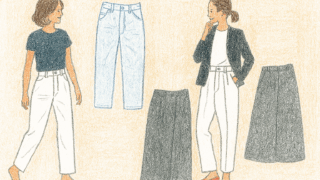
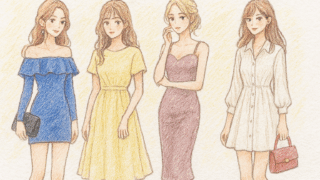


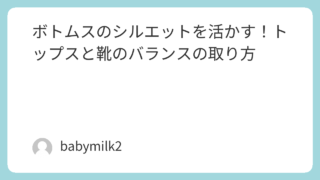

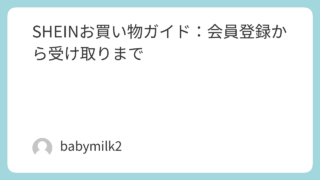




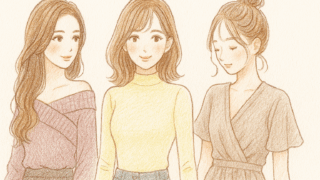
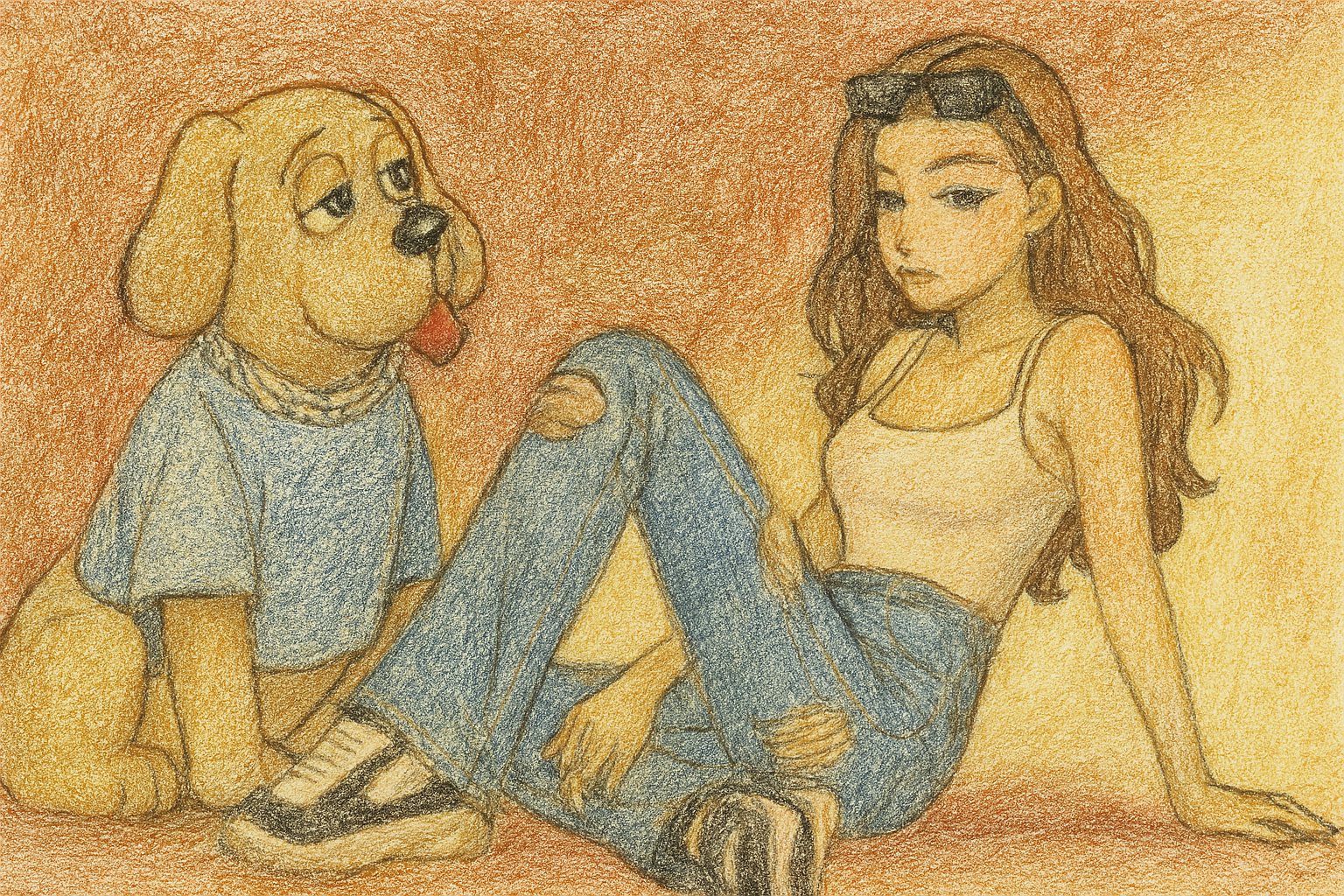



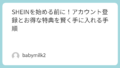
コメント